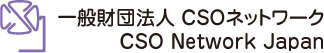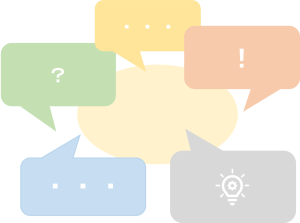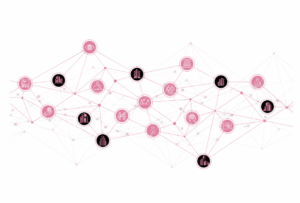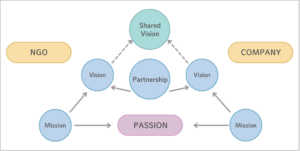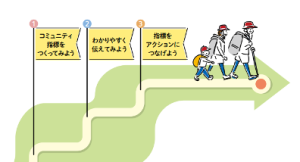PDA現地実態調査報告
~インドネシアにおける日本企業の開発支援~
<インドネシア共和国概要>
人口:2億3,760万人 (2010年度)
経済成長率(実質):6.2% (2010年度)
一人当たりGDP(名目):2,974ドル (2010年度)
主要産業:鉱業(石油、LNG、石炭)、農業(ゴム、パーム油、米)
日本の経済協力:無償資金協力 37.3億円 (2010年度)
有償資金協力 438.8億 (2010年度)
人間開発指標(HDI):124位 ※日本12位 (2011年度UNDP調査)
1. インドネシアと日本の関係
ジェトロ・ジャカルタによるとインドネシア国内において、日本企業は約1,000社進出しているといわれている。企業種は幅広く、製造業から販売業までが展開している。人口はASEAN諸国で最も多い約2億3,300万人に達しており、これは近隣のマレーシア(2,840万人)やフィリピン(9,401万人)などと比較しても格段に多いことがわかる。
日本とインドネシアは、2008年にEPA(経済連携協定)を結んでおり、人的交流として看護師や介護福祉士候補を受け入れている。インドネシアから日本へ輸出されるものは、LNGなどの燃料資源、ゴムやパーム油などの原料が中心である。
日本はインドネシアのODA主要援助国でもある。OECDによれば2009年~2010年のインドネシアへのODA総拠出額はUS$15,005 millionで、トップは日本である。日本全体のODA拠出額が一番高い国もインドネシアであった。有償資金協力は主に送電網の整備や道路建設など、インフラの整備に使われてきた。外務省によれば日本の経済協力によってインドネシア国内のダムの約3割が建設され、発電設備総容量の約20%を整備するなど、今までに多くの経済協力を日本はインドネシアに対しておこなってきた。
日本は輸入するLNGの約二割をインドネシアに依存しているため、日本にとって重要な国となっている。以上のように数字でみてくるとインドネシアの実態が少しみえてくる。このようなODAを通じてのインドネシアへの多大な支援は、インドネシアの人口の多さや国土の広さ、それに加えて豊富な天然資源を有し、中東などからの資源輸入の際の海洋戦略においても重要な位置にあることなどが要因ではないだろうか。
2. インドネシアにおける日本企業の社会貢献活動
インドネシア国内には自動車工場など多くの日本メーカーの重機械工場がある。トヨタをはじめとして、工業団地には多くの日本企業が工場を建てている。インドネシアは市場規模が大きく、日本政府もインドネシアを重要な国と位置づけてEPAを結んだり、ODAで支援をしたりしており、企業にとっても魅力的な市場となっている。
このような状況下でCSR活動を実施する企業が増えている。資源が豊富という事もあり資源採掘から生じる環境破壊を防ぐために、環境への配慮をおこなうCSR活動や工業団地設営から生じる地域開発対策まで多様に展開している。
CSRを通した社会貢献をすることで現地住民との紛争・軋轢を回避するという面もある。過去に経済開発によって自然が壊され、住民に悪影響を及ぼした例も存在するためである。よって、インドネシアにおいてCSRが課題であり不可避になっており、民間資金はCSRという形で流入していく傾向が高まっている。
企業活動をインドネシア政府が促進する一方で、インドネシア環境省が推進するPROPER(Performance Level Evaluation Program)制度がある。これは企業から提供された情報から、環境への配慮など環境パフォーマンスを評価する制度である。これへの参加自体は自主的な制度であるが、最低ランクを二年連続でとると融資をおこなわない銀行もあるなど評価の影響力はある。インドネシアは資源も豊富であり、以前から経済開発による環境破壊が問題視されていたのである。
3.インドネシアにおける日本企業の現状~BOP向けのビジネスを事例に~
民間企業の社会貢献をビジネス的観点からみていくと、日本企業の技術を活かした低所得者向けのBOPビジネスをおこなう企業もある。フマキラー(株)や(株)ヤクルト、(株)マンダムなどは好事例として取り上げられる事が多い。フマキラー(株)は高い効果や安全性を武器に、商品をまとめて売るのではなく消費者が必要な分だけ小口にして売ることで市場を開拓した。(株)ヤクルトは、低所得者層の女性をヤクルトレディとして雇い、低所得者層でも購入可能な価格を設定し、栄養素があるヤクルトをニーズに合った形で売ることで市場を開拓した。
本業に加えて、フマキラーでは健康にプラスの影響を及ぼし、ヤクルトでは栄養面の改善で生活の向上や雇用の創出を促し、社会課題解決につながっている。これらの特徴として見受けられることは、ビジネスの一方で、栄養・衛生などの人間の基本的な生活に関わる社会開発が展開されていることだ。
<参考文献>
財団法人地球・環境フォーラム、2006.3『開発途上地域における企業の社会的責任CSR in Asia』
日本貿易振興機構(ジェトロ)、2010.3『平成21年度 社会課題解決型の官民連携プログラム支援事業 (社会課題解決型ビジネスに関する 普及・啓発セミナー等事業)実施報告書(別冊)BOP ビジネスに関する 潜在ニーズ調査 インドネシア: 衛生・栄養分野』
インドネシア視察報告
主に日本企業による開発支援プロジェクトの現地視察を行うことを目的した。その他の企業の社会貢献基金や民間財団も訪問し話を伺った。
視察参加者
山内直人(大阪大学国際公共政策科教授、一般財団法人CSOネットワーク評議員)
黒田かをり(一般財団法人CSOネットワーク 事務局長・理事)
視察日程
| 3月5日(月) | 国際交流基金東南アジア総局長 小川忠様 表敬訪問 Danone Fund for Ecosystem Mr. Yann Brault, Asia Pacific Coordinator Ms. Dianne Octova |
|---|---|
| 3月6日(火) | ヤマハ発動機クリーンウォータープロジェクト現場視察 西カリマンタン ポンティアナック ヤマハ発動機、World Vision Indonesia, Wahana Bisi 現地スタッフ、村長、水委員会スタッフ等 |
| 3月7日(水) | The Asia Foundation インドネシア事務所訪問 Erman A. Rahman Director for Local and Economic Governance PT Bridgestone Tire Indonesia 訪問 ゴム農園責任者との電話会議 プカシ工場視察 |
3月5日(月)
国際交流基金
東南アジア総局長 小川忠様 表敬訪問
小川局長を表敬訪問し、CSOネットワークの事業や当視察の目的等をご説明した。
局長から、最近のインドネシアにおける日本語学習のニーズの高まりなどについてお話をいただいた。また同席してくれた元アジアリーダーシップフェロープログラムのフェローからはインドネシアの市民社会の概要などについて伺った。
Danone Fund for Ecosystem
Mr. Yann Brault, Asia Pacific Coordinator
Ms. Dianne Octova
ダノングループのエコシステムファンドは、震災後に福島の支援でCSOネットワークが(特活)日本NPOセンターとともに事前調査と事業提案をさせていただいたところである。その結果、NPO法人FAR-Net(福島県農業復興ネットワーク)が設立され、同ファンドの支援のもと、震災で被災した県内の酪農家ら14人を運営スタッフとして雇用し、共同型酪農経営モデルによる「ミネロ牧場」を福島市内に開設することとなった。酪農業だけでなく、ミネロ牧場は、学生や一般の人たちを対象に教育プログラムを実施することで、社会貢献や地域とのつながりの強化や酪農への理解の促進もはかっていく。
エコシステムファンドは、日本も含めアジアで8事業を支援している。インドネシアに6事業、インドに1事業、そしてこの福島案件である。2ヶ月に一度、社会イノベーション委員会(SIC)を開催し、助成案件を審査する。特に水、酪農、栄養プログラム、医療関連の事業を支援している。
3月6日(火)
ヤマハ発動機
クリーンウォータープロジェクト現場視察 西カリマンタン、ポンティアナック


BOPビジネス、あるいはインクルーシブ・ビジネスの代表例に挙げられることの多いヤマハ発動機のクリーンウォータープロジェクトの現地を視察させていただいた。ジャカルタに出張されていた同社は、上水道が整備されていない農村部などで安全な水を提供するために数百人規模の村落に適した小規模浄水供給システムを開発、インドネシアを初め東南アジア地域で同事業を展開している。今回は、西カリマンタンで村、国際NGO、コミュニティ団体、住民などと連携しながら進めている事業を拝見させてもらった。この事業は、同社が開発した微生物や砂ろ過を使い、水を浄化する「クリーンウォーターシステム」を用い、導入時に、その地域で立ち上げた水管理委員会がメンテナンスや管理を行う。ポンティアナックは、水道普及率が低く、村落の人々は雨水を瓶にためて沸騰させてから飲料している。政府は水を供給しているが飲むことは禁じられている。このように安全な飲み水の需要が高いこの地域で、ヤマハ発動機は、村落の人たちや、コミュニティ開発や子ども支援を行うワールドビジョン・インドネシア、その現地パートナー団体であるワハナ・ビシと連携しながら本事業を進めている。この事業により、地域コミュニティの結束も強くなったそうだ。現場を視察する前に、村長、ワールドビジョン、ワハナ・ビシ、水管理委員会のメンバーなどに話を聞いた。メンテナンスや管理のための費用をいかに調達するかという課題についていろいろな意見や提案が出された。共同組合や信用金庫からの借り入れ、メンバーからの徴収、水の販売価格の設定など、活発な議論がされていた。管理費用を助成金で賄うのではなく、ローンのほうが持続的で村のためには良いということが共有されていた。
3月7日(水)
The Asia Foundation
Mr. Erman A. Rahman Director for Local and Economic Governance
今回の事業の協力団体であるThe Asia Foundation(TAF)に表敬訪問とともに、同財団がインドネシア他アジアで幅広く展開しているガバナンスの事業について話を伺いに行った。
TAFインドネシアのガバナンスチームは、中小企業3000社以上を対象に調査を実施した。2025年には経済大国10位に入ると言われる高い経済成長率を誇っているが、水、電気などインフラが不十分であることにより事業に支障ときたしていると回答。TAFは、政策の優先順位を地域の経済成長やビジネス支援に置くように地方政府に働きかけている。この他にも、TAFはローカルパートナーとともに、2011年度にアチェの政策分析、貧困解消のために活動する市民社会イニシアチブ、国内紛争地域への支援の改善、女性の政治参加とグッドガバナンスの強化、民主化、法律セクターのリフォームなどの事業を行った。
PT Bridgestone Tire Indonesia
ゴム農園責任者との電話会議
プカシ工場視察
右田 裕隆氏、President Director, PT Bridgestone Tire Indonesia
末富 覚氏、Technical Director, PT Bridgestone Tire Indonesia, Bekasi Plantほか
 同社はスマトラ島に保有する天然ゴム農園周辺にある小規模ゴム農園に対し支援活動を行っている。PT Bridgestone Tire Indonesiaの事務所にて、PT. Bridigiestone Sumatora Rubber EstateのMr. Hicklinと電話会議で支援活動について伺った。同社は、小規模農家に対し、生産性の高い天然ゴムの苗木の寄付、タッピングの用具の提供、栽培技術やタッピンツ技術指導などを、現地でコミュニティ支援をしているNGOスイスコンタクトの協力を得ながら実施している。スイスコンタクトは、地域ネットワークを活用し、ブリジストン現地法人が実施する技術研修や支援活動の案内を小規模農家に伝える役割や、研修実施の協力などを行っている。ブリジストン現地法人、小規模農家、地域住民、NGOなどによるマルチステークホルダーの連携による取組みで、小規模農家の生産性や品質の向上、経済的自立の促進などが行われている。
同社はスマトラ島に保有する天然ゴム農園周辺にある小規模ゴム農園に対し支援活動を行っている。PT Bridgestone Tire Indonesiaの事務所にて、PT. Bridigiestone Sumatora Rubber EstateのMr. Hicklinと電話会議で支援活動について伺った。同社は、小規模農家に対し、生産性の高い天然ゴムの苗木の寄付、タッピングの用具の提供、栽培技術やタッピンツ技術指導などを、現地でコミュニティ支援をしているNGOスイスコンタクトの協力を得ながら実施している。スイスコンタクトは、地域ネットワークを活用し、ブリジストン現地法人が実施する技術研修や支援活動の案内を小規模農家に伝える役割や、研修実施の協力などを行っている。ブリジストン現地法人、小規模農家、地域住民、NGOなどによるマルチステークホルダーの連携による取組みで、小規模農家の生産性や品質の向上、経済的自立の促進などが行われている。
また、PT Bridgestone Tire Indonesiaのブカシ工場と技術訓練学校も見学させてもらった。ブカシ工場では最初に、同社のCSR活動の取組みについて話を伺った。技術訓練学校は1982 年に設置、継続的に技術者を育成している。機械系と電気系のコースがあり、2年間で研修を習得する。教育カリキュラムは70%を実技にさいている。これまで612 名の卒業生を出し、そのうち半分強がブリジストンに就職している。優秀な人材を輩出する技術訓練学校は、インドネシア工業省より社会貢献賞を受賞している。