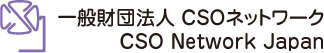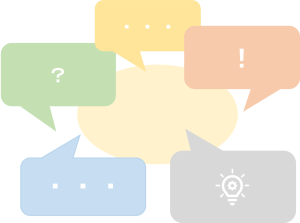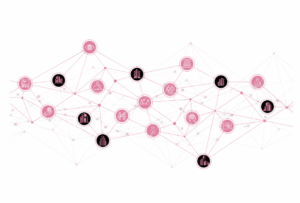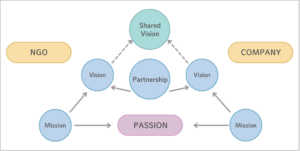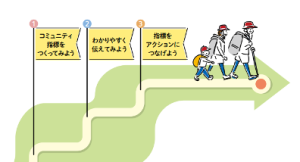外務省総合外交政策局人権人道課が10月1日から実施している「ビジネスと人権」に関する行動計画改定版についてのパブリックコメントに意見を提出しました。25項目の意見の全文は以下のとおりです。
※ 行動計画改定版原案及び意見募集要領は、下記の「電子政府の総合窓口」サイトからダウンロードできます。
「ビジネスと人権」に関する行動計画改定版の原案についての意見募集
全体に関わる意見
意見①
多くの紙幅が費やされている冒頭の「2020~2025 年の取組成果」の記述内容は、「取組成果」というよりも「取組内容」というべきものであり、国の人権保護義務の履行のためにどのような施策を行い、その結果、人権はどの程度保護されるに至ったか、というビジネスと人権の行動計画として本来記述すべき内容はほとんど見られない。この点は「優先分野」の各項目にある「課題認識及びこれまでの取組」の記述も同様で、ほとんどがこれまでの取組を示すにとどまっており、課題認識については記載がないものが多い。国連ビジネスと人権に関するワーキンググループの「国連ビジネスと人権に関する国別行動計画の指針」(以下「NAPガイダンス」)には「NAPは各国の現実の状況に対応し、ビジネスに関連する現実のまたは潜在的な人権侵害に対処する必要があること」とあるように、旧計画が実現を目指すとしていた内容がどの程度実現できたかを記載した上で課題認識を記載する必要がある。なお、課題認識の記載にあたっては、少なくとも、2024年の国連ビジネスと人権作業部会の訪日調査報告書で指摘された日本の人権課題を踏まえる必要がある。
意見②
「優先分野」の各項目での「課題認識」については、NAPガイダンスも「行動計画の改定は、企業に関連する人権への負の影響を防止・軽減・救済するために既存の行動計画が実際にどの程度効果があったかについての徹底した評価に基づくべきである」としているように、本来は、従来の施策を検証した上で課題を記載し、その検証結果に基づいて「取組の方向性及び具体的施策の例」を記載すべきだが、現状は施策を評価するための適切な指標が設定されていないため検証が不可能となっている。したがって、新計画の「優先分野」においては、少なくとも新計画の各施策について、「ステークホルダーとの協議の上でアウトカム指標を設定し、検証を行う」ことを記載するべきである。
第2章 優先分野 1 人権デュー・ディリジェンス及びサプライチェーン
意見③
「課題認識及びこれまでの取組」の中で多用されている「サプライチェーン」が、いわゆる上流と下流の双方を含むのかどうかの改めての定義がやはり必要である。「環境と人権」の部分では「バリューチェーン」が使われており、一般の読み手を混乱させないためにも用語の統一と意味の定義が必要である。
また、「サプライチェーン」が上流と下流双方を含むとすれば、この部分では、消費者の権利への負の影響や、投資家・金融機関による投融資が及ぼしうる人権への負の影響など、下流に関連する「課題認識及びこれまでの取組」も記述するべきである。「2023年6月の「OECD多国籍企業行動指針」の改訂により、企業によるサプライチェーンの下流へのデュー・ディリジェンスの適用範囲が明確化された」(4ページ)との認識を生かし、この部分でも具体的に展開することが求められる。
意見④
「課題認識及びこれまでの取組」第1段落の「企業においては、自社・自社グループの職場におけるハラスメント、安全衛生、過重労働、差別といった人権リスクに加え、取引先及び社会的に弱い立場にある外国人労働者、女性、LGBTQ、障害者、非正規労働者等のライツホルダーの人権リスクにも関心・問題意識が集まっている。」の部分は、「課題認識」としてさらに具体的に記述する必要がある。国の人権保護義務を果たすための「課題認識」としては、指導原則の示すとおり、企業の人権デュー・ディリジェンスが、ライツホルダーの人権への負の影響を適切に把握して防止・軽減するものになっているかどうか、それが不十分であれば、人権デュー・ディリジェンスを国としていかに促進・支援するか、を記述する必要があり、「関心・問題意識が集まっている」という単なる状況認識の記述は妥当ではない。さらに、この部分では、「職場における人権リスク」「取引先の人権リスク」「ライツホルダーの人権リスク」が並べられているが、実際にはそれぞれのリスクが重なりあって存在しているのが現実であるため、分かりやすく整理して記述する必要がある。
意見⑤
「取組の方向性及び具体的施策の例」①の「円卓会議・作業部会」の継続については、この「人権デュー・ディリジェンス及びサプライチェーン」の課題に関して何をどのように議論するのかを記述し、実効性のある議論になるように具体的な議論のあり方を記述する必要がある。
第2章 優先分野 2 「誰一人取り残さない」ための施策推進 (2)外国人労働者
意見⑥
来日する外国人労働者が、来日前の段階で多額の借金を背負う事例や、事前に聞いていた業務内容や労働条件と異なる環境におかれる事例が依然として報告されている。また、日本の生活環境や労働慣行に関する情報が十分に届かないまま来日するケースも多く、外国人労働者が自らの権利や選択肢について適切に判断することが困難な状況がある。就労環境の改善だけでなく、外国人労働者の尊厳と、基本的人権としての職業選択の自由を保障する観点からの課題の記載が「課題認識及びこれまでの取組」において必要である。
意見⑦
「取組の方向性及び具体的施策の例」において、現在記載されている施策に加えて次の施策が必要と考える。「外国人労動者の来日前の段階からの権利保護と情報提供の強化」。
来日前に十分な情報が行き届かないまま来日し、高額な費用負担や希望と異なる職務内容に直面する外国人労動者が依然として多く存在する現状をふまえ、政府間協議や民間の取り組みを含めた包括的な施策が求められる。
また、JICAが進める「求人情報へのアクセス支援プロジェクト」や、JP-MIRAIが実施予定の「公正なリクルートメントの認証制度」など、送り出し国での情報アクセスと透明性の確保に向けた取組が進められており、これらを踏まえて更なる官民連携を促進する施策が必要である。
意見⑧
「取組の方向性及び具体的施策の例」において、現在記載されている施策に加えて次の施策が必要と考える。「外国人労動者の人権尊重の促進に向けた公共調達政策の活用」。
外国人労働者の権利保護を実効的に進めるためには、企業の自発的取組みに加え、政府調達における人権尊重の要件を明確にし、外国人材の適正な雇用・処遇に取り組む事業者を積極的に評価・選定する制度設計とする施策が必要である。
また、政府や自治体の調達において、人権尊重を重視した調達ガイドラインを策定し、企業の行動変容を促すためのインセンティブとして活用すべきである。【内閣官房、厚労省、各省庁調達担当部局】
意見⑨
「取組の方向性及び具体的施策の例」において、現在記載されている施策に加えて次の施策が必要と考える。「外国人労働者と企業との対話促進および多文化共生に関する企業向け支援」。
外国人労働者の就労環境の改善には、労働条件の整備のみならず、企業内におけるコミュニケーションや文化的相互理解の促進が不可欠である。企業が外国人とともに働くための組織的な対応力を高めることは、持続可能な雇用関係の構築につながる。
そのため、企業向けの多文化共生に関する研修の実施や、外国人労働者との対話を支援する仕組みの整備を、国や自治体が支援・促進するための施策が望まれる。具体的には、社内相談窓口の多言語対応、定期的な意見交換の場の設置に加え、利害関係のない第三者による外国人労働者へのヒアリングを導入することにより、本人が安心して声を上げられる環境を整える、などが考えられる。【厚労省、法務省、自治体】
第2章 優先分野 3 テーマ別人権課題 (2)環境と人権
意見⑩
「環境と人権」に関わる具体的な課題、つまり環境への負の影響がどのように具体的に人権に負の影響を及ぼしているのかについての記述が、「課題認識」として必要である。例えば参照されているだけの「環境デュー・ディリジェンスに関するハンドブック」に一部記述されている負の影響に関する内容を、ここでも具体的に展開する必要がある。記述されている欧州の法規制の動き等への対応は企業としての課題であり、国の行動計画での「課題認識」として記述すべき「環境と人権」をめぐる問題自体の課題ではない。
意見⑪
「取組の方向性及び具体的施策の例」①の項目には「補助金事業等における企業による人権尊重の取組の審査基準項目への組入れ」とあるが、審査基準項目の単なる追加ではなく、環境課題が人権課題に直接関わることを視点として組み入れた項目にしていく必要がある。
意見⑫
「取組の方向性及び具体的施策の例」②の項目の具体的な施策として、「公正な移行」への対応を促進する視点からの施策を追記するべきである。また気候変動、生物多様性の損失及び汚染という相互に関わり合う3つの課題の対応のためには、脱炭素、自然再興の取組(ネイチャーポジティブ)、循環経済等の総合的な対処が求められている。よって「気候変動への適応と緩和政策」だけでなく、自然再興の取組と循環経済への移行の視点も加えた上で「人権への配慮」とすべきである。
第2章 優先分野 5 企業の情報開示
意見⑬
「課題認識及びこれまでの取組」4段落目の「ステークホルダーへの説明」の叙述は不十分であり、さらに敷衍する必要がある。つまり、企業の人権尊重責任の取組は企業のみで行うことでは足りず、ライツホルダー等のステークホルダーとの対話・エンゲージメントによってより効果的な信頼できるものとなり、また、企業による情報開示が、とりわけ負の影響を受けるライツホルダーとの対話・エンゲージメントの促進につながる、との観点を挿入するべきである。具体的には、「投資家にとっては」の前に、「企業の取組から負の影響を受けるライツホルダー等は負の影響を受けた場合の企業の是正・救済にあたって、企業と対話・エンゲージメントを行うことによって適切な是正・救済につながり、またそうした対話・エンゲージメントは企業の取組の信頼性の確保にもつながることを認識する必要がある。」との一文を挿入するべきである。
意見⑭
「取組の方向性及び具体的施策」の施策項目には、企業の情報開示にあたっての重要なステークホルダーである消費者への視点が欠落している。企業活動は消費者の権利(消費者基本法第2条)にも重大な影響を及ぼすのであり、具体的施策として欠かすことはできない。企業の適切な情報開示に依るところが大きく、逆に企業の適切な情報開示を促進することにもなるエシカル消費の促進など、下記の施策項目を追記するべきである。
・「人や環境に配慮した消費行動であるエシカル消費の促進【消費者庁】」
・「企業の取り組みに対する消費者の理解と評価を進めるための企業の適切な情報開示の促進【消費者庁、外務省】」
また、第1章の「2 日本企業の取組状況と国際的な動向」ではサステナビリティ基準委員会(SSBJ)などサステナビリティ関連非財務情報の開示の動きについて記述されているが、企業のみならず、これらの動きから間接的に大きな影響を受ける消費者の視点から、消費者庁としての施策を検討していただきたい。
第2章 優先分野 6 公共調達・補助金事業等を含む公契約
意見⑮
「課題認識及びこれまでの取組」に、2023 年 4 月に決定された「公共調達における人権配慮について」の政府方針の具体的な取組内容が記載されていない。しかし、「公共調達のプロセスを通じて、企業の人権尊重の取組が促進されることが重要」であることを踏まえれば、政府方針によって実施された関係省庁の公共調達を通じた具体的な取組を記載するとともに、それらの取組が企業の人権尊重をどのように促進させたかについての評価と、評価に基づく課題が記述されるべきである。
また、公共調達の透明性の向上、人権リスクの特定・評価やモニタリングにおけるステークホルダーとの対話などは、これらが進んでいる海外の公共調達の取組に比べて、日本の公共調達における課題となっており、この点についての記述も必要である。
意見⑯
指導原則では、企業の人権尊重を促進すべく、政府にもデュー・ディリジェンスを実施する義務があるとしている。「政府方針」の具体的取組として、公共調達に関して行ったデュー・ディリジェンスに関する情報開示、公共調達を実施する省庁・機関によるグリーバンスメカニズムの設置等への検討を「取組の方向性及び具体的施策」として記述するべきである。
意見⑰
「政府方針」を受けて、公共調達の中の個別分野における人権尊重の組込みが必要である。既存の女性活躍、障害者就労などの取組みに加えて、「外国人労働者」をはじめ少なくとも第2章「優先分野」の「2「誰一人取り残さない」ための施策推進」に掲げられている個別分野については、公共調達に組み込むべき具体的な人権の取組として「取組の方向性及び具体的施策」に記述するべきである。
意見⑱
「課題認識及びこれまでの取組」で「公共調達の参加要件に(人権尊重を)盛り込むことで中小企業が公共調達から排除され得ることに対する懸念」が示されているが、全国の地方自治体の中には、東京都のように社会的責任調達指針を定めて人権尊重の遵守を掲げている自治体や、入札の仕組みの中に人権研修や取り残されがちな人々に対する独自の基準を設けている自治体もある。政府においても、中小企業の当該分野における能力構築について、関係各省及び地方自治体との連携も含めた今後の方向性などを検討する旨の記載が「取組の方向性及び具体的施策」において必要である。
第2章 優先分野 7 救済へのアクセス
意見⑲
「課題認識及びこれまでの取組」では、現在の制度や認知度については数多く列挙されているが、ライツホルダーの人権がその制度によっていかに実効的に救済されてきたかという観点での記載が欠如している。「実効性を高めていくことが課題」(32ページ)であると認識し、「救済の仕組みを重層的に整備することにより、実際の人権侵害の救済に結びつける」ことを「期待」(32~33ページ)するのであれば、現在の制度が旧計画の期間を通じてどの程度実効的であったかを具体的に記述する必要がある。
意見⑳
「新計画においては、ステークホルダー報告書等で取り上げられた様々な課題及びその後の議論を踏まえた」(11ページ)とされているが、そのステークホルダー報告書ではNCPについて、「第2回ピア・レビュー等において、ステークホルダーとの対話・エンゲージメントの機会を設定する」ことが提案されている。「取組の方向性及び具体的施策の例」でのそれを踏まえた記述とみられる①では、「ステークホルダーとの対話・エンゲージメントの機会」の具体的な方法、例えば円卓会議や作業部会のメンバーのネットワークを活用して行うなど、具体的な方法まで記述する必要がある。
意見㉑
ステークホルダー報告書で言及されている国内人権機関の設置が、「取組の方向性及び具体的施策の例」②の「人権救済制度のあり方の検討を継続」との記述には含まれていない。「各種救済制度が、実際の人権侵害の救済に結びつくものであることが必要」(32ページ)であるなら、より具体的に「パリ原則に合致した国内人権機関の設置を含めた人権救済制度のあり方の検討を継続」とする必要がある。国内人権機関については指導原則で、非司法的苦情処理メカニズムにおいて「国内人権機関が特に重要な役割を果たす」とされているほか、国連ビジネスと人権作業部会の訪日調査報告書も、「パリ原則に沿って堅固で独立した国内人権機関を遅滞なく設立すること」を政府に勧告している。
第2章 優先分野 8 実施・モニタリング体制の整備
意見㉒
「課題認識及びこれまでの取組」の3段落目では、「旧計画が定める各分野における「今後行っていく具体的な措置」については、年次レビューにおける「行動計画施策実施状況一覧」のとおりそれぞれ進展を見せており、旧計画の目標の達成に向け、着実に前進している」との記述があり、同様の記述は第1章にもみられる(6ページ)。しかし、87に及ぶ広範な施策のうち、エビデンスとして示されているのは、経団連による調査結果を引用したかたちでの「指導原則に基づき取組を進めていると回答した企業」の割合という1つのアウトプット指標だけである。「着実に前進している」と記述するためには、「行動計画施策実施状況一覧」で報告されている87施策について、設定されている指標自体の現状、及びその指標によって測られた施策の進捗状況を総合的に示す必要がある。それがないと「着実に前進している」とは記述できず、また意味のある課題認識も導き出すことができない。
意見㉓
「課題認識及びこれまでの取組」の末尾では、「ステークホルダーとも協議しつつ」だけではなく、より具体的に、「具体的には新計画策定後速やかにステークホルダーとの検討の場を設けていく」旨を記載するべきである。
第3章 政府から企業への期待表明
意見㉔
3段落目の「近年、日本社会において、企業活動の人権に対する影響に更に注目が集まっており、企業の対応が自らの存続に関わるものとなっているケースも見られる。そのため、人権リスクはどの企業にもあることを前提に、危機管理の一環として人権を捉え、対応することが求められている。」の部分は、企業の経営リスクへの対応を軸とした記述になっているが、前提として、ライツホルダーの人権への負の影響に対処する人権尊重責任が企業にあることを同程度以上のウエイトで記述する必要がある。加えて、この部分の前段は人権リスクと経営リスクの関係が未分化のまま混在した記述になっており、改善が必要である。
第4章 今後の行動計画の実施及び見直しに関する枠組み
意見㉕
旧計画では「2020-2025」という期間の記載が文書名にあったが、新計画の原案にはそれがない。新計画終了後の改定については、「公表から5年を目途に「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」において、必要性を適切に判断する」とされているが、計画は本来、その実施期間を設定すべきものである。「NAPガイダンス」も、行動計画の定期的なレビューと改定は、行動計画の不可欠の基準であるとしている。また、旧計画では「公表4年後を目処に、関係府省庁連絡会議において、ステークホルダーの意見も踏まえ、行動計画の改定作業に着手する」とされていたが、新計画では「ステークホルダーの意見も踏まえ」の部分が割愛されている。改定の「必要性を適切に判断する」際には「ステークホルダーとも協議する」旨の記載が必ず必要である。
■